【大学生シリーズVol.1】社会人と“本気”で向き合った3カ月──「二枚目の名刺」で広がった世界
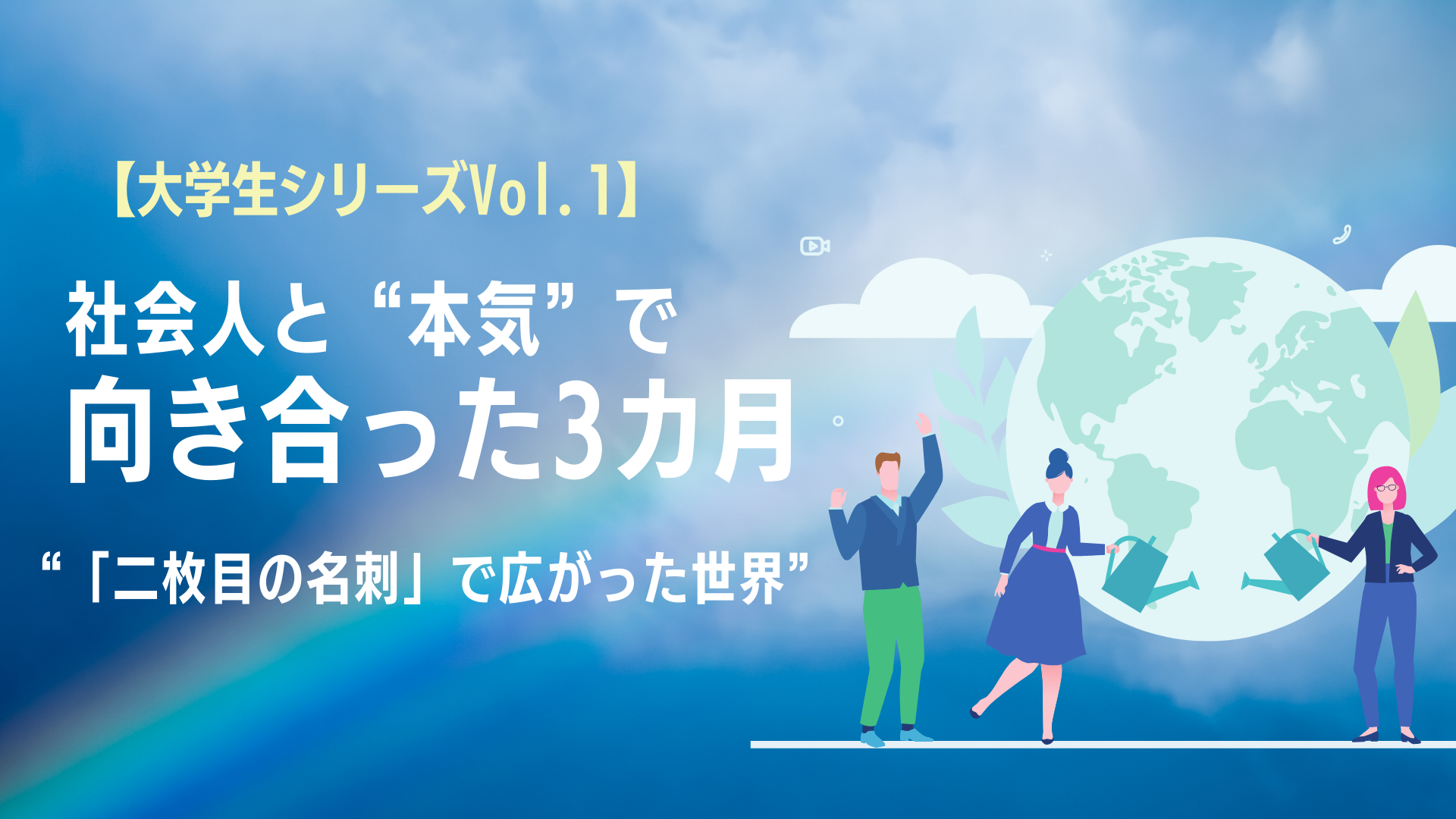
学生のうちに社会人と一緒にプロジェクトに取り組み、自分の視野を大きく広げた3人の大学生。彼らは「二枚目の名刺」のインターンシップに参加し、NPOのサポートに携わる中で、社会の多様さや自分の可能性を体感していきました。ここでは、木嶋さん・拜詞(はいし)さん・大木さん、それぞれの体験をインタビュー形式でご紹介します。
木嶋さん(大学3年生(参加当時) /女性)
Q. 「二枚目の名刺」サポートプロジェクト参加時の活動内容を教えてください
木嶋:NPO法人SETが運営している「いわてユースセンター ミライト」という交流スペースで、2024年7月1日から10月19日までの約3カ月間活動していました。具体的には、寄附金を集めるための第1ステップとして、メールマガジンの運用やホームページの刷新などに取り組みました。
ユースセンターとは、学校でも家でもない、中高生を対象とした第三の居場所です。私自身、地域福祉というジャンルに興味があったため、ミライトで活動しようと思いました。
Q. 「二枚目の名刺」に参加したきっかけは?
木嶋:学生が少ないと聞いていて、正直緊張と不安はありました。でも、福祉を学びながら、違う分野にも視野を広げたいという思いがあって、それが叶うんじゃないかと思って参加を決めました。
Q. 実際に始まってみてどうでしたか?
木嶋:最初は年齢や人生経験の差を強く感じました。雑談の中でも、語彙力や話の切り出し方の違いがあって、私だけ置いていかれるような感覚もありました。でも、皆さんが私を社会人の一員として、時には親のように接してくれて、フラットな関係性を築くことができました。そのため、とても居心地の良い場所でした。
他に知り合いもいない団体であったため、逆にのびのびと活動できたとも思っています。
Q. オンライン中心での活動で大変だったことは?
木嶋:やっぱり人間関係の構築が難しかったですね。でも、一度だけ全員で対面する機会があって、それがターニングポイントになりました。最初は対面することに不安がありましたが、あの時間があったからこそ、チームとしても私自身も一気に距離を縮めることができました。
Q. 苦労したことは?
木嶋:実習と両立しながら、ミーティングのファシリテータも担当したことです。年上の社会人を前に、会議を回すのはとても緊張しました。でも、先輩方の進め方を見て学びながら、回数を重ねて少しずつ慣れていきました。
特に、ファシリテーターの役割として、「その日の打合せで、何をゴールにして何時間話すかといった点」が大切であるとわかったことは、大きな学びとなりました。また、他の参加者からの意見を引き出すことの重要性も身をもってわかるようになりました。
メールマガジンの運用やホームページの刷新といったことは、初めての経験であったため最初は不安がありました。でも、求められていることが学生ならではの視点で意見を出してほしいとのことだったので、今回の活動に貢献できたと考えています。
Q. 活動を通して学んだこと・得られたことは?
木嶋:活動の前半は、主に壁打ちをしていました。そのときは、壁打ちをする意味や必要性がわからない状態で参加していました。後半に入って、実際に活動に本格的に取り組むようになって、前半の壁打ちをした意味がわかり、準備や試行錯誤の時間も大切であると実感しました。
一緒に活動していた社会人の方の行動力や、モチベーションの高さなどがひしひしと感じられ、私も頑張らないとと励みになりました。また、社会人の方のマインドに触れることで、私も行動力が身に付き、積極的に活動できるようになりました。
Q. 就活にも役立ちましたか?
木嶋:面接で「学生時代に頑張ったこと」を聞かれた時に、必ず「二枚目の名刺」の経験を話しています。今もNPOとつながり続けてメルマガの運用をお手伝いしている点も含めて、面接官の方に高い評価をしてもらえることが多いです。
Q. 最後に、これから参加を考えている人へメッセージをお願いします。
木嶋:学生1人で社会人に交じるのは不安かもしれません。でも、それが逆に成長のきっかけになります。社会に出る前のこの時期に、社会人とフラットに関われる経験は本当に貴重だと思います。ぜひ飛び込んでほしいです!
拜詞さん(大学3年生(参加当時) /男性)
Q. 「二枚目の名刺」サポートプロジェクト参加時の活動内容を教えてください
拜詞:愛知県岡﨑市を拠点としている、「コネクトスポット」という地域福祉を支援しているNPO法人で活動していました。活動時期は、2024年9月から11月までの約3カ月間です。
実際に僕が活動した内容としては、コネクトスポットという団体が存在する意義を、見つめなおすことから始めました。見つめなおすことによって、団体が目指すべきゴールや理想像を明確にしていきました。
理想像が明確になるにつれて、今やらなければならないことは、地元岡﨑市民の方たちへの認知度を上げることという結論に達しました。そこで、どういった方法で情報発信をしていくべきかについて検討してきました。
Q. 「二枚目の名刺」に興味を持ったきっかけは?
拜詞:もともと不登校や引きこもりの子どもたちの支援に関心があって、そうした団体を探していたんです。そこで、これらの活動を支援しているコネクトスポットという団体に惹かれて、参加を決めました。
Q. 実際の活動はどうでしたか?
拜詞:最初は自分が思っていた支援内容とは少し違っていて戸惑いもありました。でも、活動を通じて自分が全然想定していた以外の領域、たとえば地域福祉にもかかわらせていただくことができ、いい経験になったと思っています。
Q. 苦労したこと、戸惑ったことは?
拜詞:ミーティングでの発言の仕方や、意見のまとめ方に社会人の方との差をすごく感じました。社会人の皆さんは、課題を多角的に捉えて意見を言うのがとても上手で…。僕はある課題に対して、1つの面だけを見て考えることが多く、そこにすごくギャップを感じて悩みました。
Q. どんな成長がありましたか?
拜詞:最初はプレッシャーもあって挫折しかけましたが、支えてくれる人がいて、なんとか最後までやり切れました。特にデザイナーさんから「自分なりにできることをやった方がいい」と励まされたのが大きかったですね。
また、社会人の方と活動することで、自分のことを客観視できるようになり、今の自分に「足りていない」ことが、わかったという点も大きな収穫でした。
Q. 就職活動にもつながりましたか?
拜詞:すごく影響がありました。以前は面接もアドリブでなんとかなると思ってましたが、この活動を経験することで「しっかり準備してから挑む大切さ」を痛感しました。事前準備ができてはじめてスタートラインに立てるんだなって。
Q. 後輩へのメッセージをお願いします。
拜詞:たぶん、最初は誰でも不安だし、うまくできないこともあると思います。でも、それが当たり前。むしろ失敗して、そこから自分を見つめ直すきっかけになるのがこのプログラムだと思います。社会人と本気で向き合う3カ月、やって損はありません!
大木さん(大学3年生(参加当時) /女性)
Q. 「二枚目の名刺」サポートプロジェクト参加時の活動内容を教えてください
大木:アフリカのマラウイで学校給食支援を行う団体である、「せいぼじゃぱん」というNPO法人で活動をしていました。活動期間は2024年8月から10月までの3か月間です。この団体が抱えている課題の解決や、事業推進などの活動に取り組んでいました。
具体的には、団体の活動に賛同してくれる会員集めについて、他のメンバーとアイディア出しをしました。また、団体を知ってもらうために、大学で開催したワークショップの企画や運営を行いました。
ワークショップに参加した学生からは、「マラウィという国を初めて知った」「せいぼじゃぱんの活動に関心を持った」など、さまざまな反応がありました。
Q. 参加のきっかけは?
大木:社会福祉を学ぶ中で、私は「国際福祉」に興味がありました。いくつかの団体の中から、国際福祉に取り組んでいる団体であったため、「せいぼじゃぱん」に参加しようと思いました。
Q. 活動を始めたときの印象は?
大木:最初はとにかく緊張しました。社会人の方ばかりの中に学生1人。ついていけるかすごく不安でした。でも、最初のミーティングから皆さんがとても温かく迎えてくださって、少しずつ自分も発言できるようになっていきました。
また、学生であっても対等な関係で、意見を出したり聞いてくれたりしたため、他のメンバーに溶け込みやすかったです。
Q. 苦労したことは?
大木:週1回定例ミーティングを行っていたのですが、司会や議事録作成は輪番制で行っていました。私の場合、司会や書記の仕事が未経験であったため、最初はかなり苦労しました。
Q. 活動を通して得たものは?
大木:社会人の方々の話し方や考え方を間近で学べたことです。特に「話の組み立て方」「相手に伝える姿勢」はとても勉強になりました。自分の考えをきちんと伝える練習にもなったと思います。
Q. 活動後もNPOとつながっていますか?
大木:はい、今でもやりとりがあります。2025年7月にせいぼじゃぱんのメンバーが、大学でワークショップを開催するのですが、私も自分が経験したことを伝える機会をいただいています。
Q. これから参加を考えている人へメッセージをお願いします。
大木:迷っているなら、ぜひ一歩踏み出してほしいです。不安があっても、きっとその先に「やってよかった」と思える経験が待っていると思います。社会人と本気で関わることで、自分自身の成長を実感できるはずです。
ライター
編集者
カメラマン
