実録・越境学習がもたらした、社会人とNPOの変化とは?【後編】

2016年9月30日に行われた、日本財団ソーシャルイノベーションフォーラム2016のセッションから、「2枚目の名刺が社会人やNPOにもたらすものは何なのか」を紐解いていきます。
社会人メンバーに訪れた最初の試練>【前編】はこちら
ーーーーー
目的を擦り合わせることで、プロジェクトがうまく回り始める
ホーム、すなわち企業の中では、皆が同じ社内用語を話し、近しい価値観を持っているため、プロジェクトも比較的スムーズに進みやすい。しかし、サポートプロジェクトに参加すると、それらが一切通じない。メンバー間で“言葉の定義”が異なるのだ。そこにアウェイのプロジェクトを進めることの難しさがある。
金澤さん「皆が団体の思いや取り組みに共感していたし、使っている言葉も同じ。最初はメンバー間の目線が合っていると思っていましたが、2ヶ月目くらいに共通認識が全く異なることがだんだん表面化してきたんです」
それでも3ヶ月目から一気にプロジェクトがうまく運び、最終的に納得のいく提案ができたのは、「何のために自分たちがこのプロジェクトをしているのか」という目的をメンバー内で共有できていたからだ。
1枚目の名刺を持つメンバーが、忙しい中で時間を作り、無報酬のプロジェクトに取り組むためには、「何のためにこのプロジェクトをするのか」「何を達成したいのか」ということを徹底的に話し合い、擦り合わせをしておかないとプロジェクトがうまく回らない。
サポートプロジェクトには指示を出してくれる上司もいなければ、アウトプットに対する正解もない。その中で、団体の出す本質的なお題を解決するためにはどうすれば良いのかをゼロから考えなければならない。この“曖昧な中で考え、自分自身で意思決定する”というプロセスが、企業の中では得られない経験や成長につながる。
本質を見る目を養うことが、イノベーションにつながる
金澤さんらのプロジェクトチームが納得のいく成果を出せた理由の一つに、「団体側の想いや活動の動機がしっかり伝わっていた」ことが挙げられる。NPOの活動のもととなる“志の源泉に触れる”という経験もまた、企業の中ではなかなか得ることができないものだ。社会人メンバーと目線を合わせてプロジェクトを進めるにあたり意識した点を、朝山さんはこう話す。
朝山さん「私たちの理念に共感してくださっている方とやりたいと考えていました。いくら第三者的な目が必要だとは言っても、根底部分への共感がないと、互いにズレが生じてくると思ったので」
サポートプロジェクトでは、二枚目の名刺のコーディネーターが団体とプロジェクトチームの間に入り、チームの編成等、様々な調整役を担っている。そこでもやはり、ミッションへの共感を大事なポイントの一つに置いている。
朝山さん「一緒にやっていく中で、イノベーションを起こす人材を今企業が育てたいと思っていることも、NPOへのサポートプロジェクトを活用される理由も段々とわかるようになりました。熱意ある若手の人材が、実際に活動しているNPOに飛び込んでくることで、本質を見る目を養うことができ、自分が心動かされる社会課題に出合ったときに、イノベーションは起きていくんだろうと思います。」
マネジメントスタイルの変化と、社会に対する当事者意識の芽生え
サポートプロジェクトを経験することで、その後の社会人にどんな変化があるのだろう。金澤さん自身の現況を見てみよう。
金澤さん「まず大きな変化の一つとして、マネジメントのスタイルが変わったことが挙げられます。“多様性のあるマネジメントを実践する”ことが参加目的の一つにありましたが、プロジェクトを経験したことで、きっちり役割分担をし、人を巻き込みながら物事を進めていくマネジメントスタイルを身につけることができました」
これまでは、チームメンバーの誰よりも自分が頑張り、“背中を見せて引っ張る”というスタイルで、1チームのマネジメントをするのが限界だったが、現在は4チームのマネジメントを担当し、仕事の幅も広がっている。
金澤さん「もう一つの変化は、自分自身が社会に対して当事者意識を持てるようになったことですね。正直、サポートプロジェクトに参加するまでは、社会問題に対する関心があまりなかったんです。でも、Common Room(※)で朝山さんの話をお聞きし、熱い思いに胸を打たれ、プロジェクトに参加したことで視野が広がったように思います」
※Common Room: NPOと社会人の出会うマッチングイベント。このイベントから、サポートプロジェクトの立ち上げが行われる。
こうした自身の成長経験を、より自社内に広げようと、現在次のステップに取り組んでいる。自らが二枚目の名刺「サポートプロジェクト」のモデルを社内で創る側となり、人事部と一緒にNPOを探し、社内でプロジェクトを立ち上げている。2枚目の名刺を持つことの素晴らしさを、多くの人に伝えていきたいのだ。
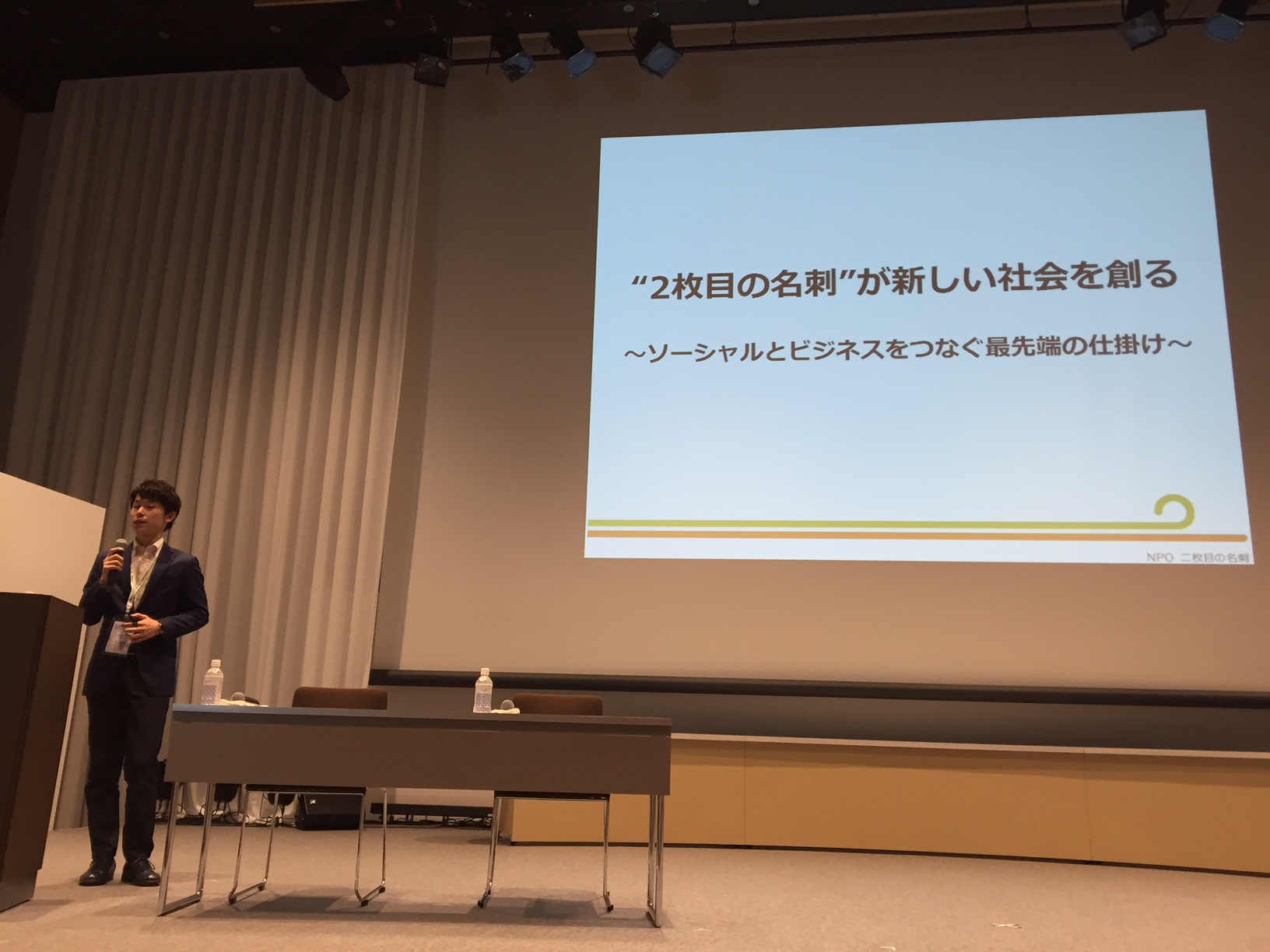
2枚目の名刺を持った人から、変化の輪が広がっていく
組織の枠を飛び出した社会人が、業界・業種やバックグラウンドの異なるチームの中で、社会に新しい価値をゼロから生み出していく。こうしたプロジェクトからうまれた価値が、NPOの掲げる社会課題を解決する契機の一つとなり、同時に、普段とは異なる環境で本気で取り組んだ経験が、社会人の成長や企業にイノベーションをもたらす糧になる。サポートプロジェクトを経験した社会人が、そのモデルを持ち帰り、企業の中でも実践し、広げていく。そこから企業組織にも変化の火種が起き、社会に派生していくのだろう。
これまで、企業とNPOの協働は、社会貢献活動やCSRという文脈で捉えられることが多かった。一方、サポートプロジェクトで協働した社会人とNPOは、社会の変化に一緒に挑戦し、その取り組みを通じて共に新しい変化のきっかけを掴んでいる。社会人・NPO・企業へのイノベーションを同時に実現する可能性を秘めている、これが二枚目の名刺のサポートプロジェクトが今、注目を集める理由なのかもしれない。
文:はしもとゆふこ(二枚目の名刺)
ライター
編集者
カメラマン
